マーケティングツールのあるべき姿とは
ツールの方向とターゲット
当社を含め多くの企業がデジタルマーケティングツールを提供しています。
一口にマーケティングツールといっても、それは集客なのかコンバージョン向上なのかCX向上なのかUX向上なのか、そのジャンルはさまざまです。
そうした中でよく思うのが、「それはどっちを向いているツールなのか」という疑問です。
もちろん当社を含めの話であり、自己や自社への戒めも含めてなのですが。
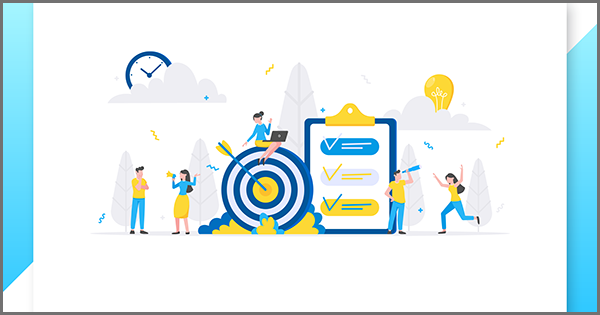
数年前のとあるマーケティングイベント内の勉強会で、ツールベンダーのあるべき姿といったテーマを取り上げたことがありました。
「製品のセールス時は都合の良いことを言うが、一旦導入を決めた後は途端に対応が悪くなることが多い」というブランド企業やリテール企業の不満について、真摯に向き合おうというような内容です。
その中であくまでその解決への一事例として「製品の価格を高くする」という当社の取り組みを紹介したところ、(良い意味で)「驚きました」というコメントをいただいたことがあります。
製品の価格を十分高くしてそれに見合った機能を搭載できれば、無理なセールストークをすることもなくなるし、導入後のサポートを惜しむ必要もなくなります。
とはいえもちろん、価格を高くし過ぎて売れなくなっては元も子もありません。
問題は、そうした十分な機能とサポートを提供できる価格帯が需要と供給の価格曲線の交差する点と大きく乖離している場合どうしたらいいのか、というものだと思います。
つまり、十分な機能とサポートを提供しようとすれば、製品の価格競争力がかなり低くなってしまうケースということですが、実際こうしたケースはたくさんあるのではないでしょうか。
マーケティングツールの適正価格
その場合に取り得る解決策はいくつかあります。
まずは製品の費用対効果を高めるという当たり前の方法です。
例えば一機能の追加にコストとして1000万円かかる場合、その機能追加によって見込める粗利(粗利というのがポイントです)がそれを1年程度で上回るならそれは良い取り組みであると言えるでしょう。
次に製品の開発効率を上げるという手段もあります。
上記の例で1000万円かかるところを600万円で実現できれば、より有効なアプローチとなります。
ただ開発効率を上げるには良い手段と悪い手段があります。
例えば作業効率を上げるために開発環境やライブラリなどを整備する、開発のフローやルールを最適化する、などはトレードオフとなるデメリットがほとんどありません。
しいていえば短期的に負荷が上がる可能性があるということくらいです。
一方で、単純に人件費を削るなどは良いとは限りません。
例えば過剰に外注先のリソースを使用しているのを見直すなら悪くはないですが、外注先を内製に切り替えるのはそれなりの覚悟は必要です。
他にも販売効率を上げるという方法もあります。
結局「販売コストが製品の粗利を超えると赤字」なのですから、売って得る粗利以上に販売コストがかかるのは製品の立ち上げ時を除けばほぼ悪手ということになります。
究極の手段として「そのジャンルからは一時的もしくは永続的に撤退する」という選択肢もあります。
参入する市場の見極めと好機
結局過当競争なマーケットで十分クライアントに満足してもらえるようなサービスレベルを実現できる規模の粗利を得るというのは、そもそも無理があります。
ただいわゆるハイプサイクルに見られるように、とあるジャンルが一時的に過熱し、参入している企業群のサービスレベルが下がって行きいずれ幻滅期を迎えたその後、つまりマーケットがある程度成熟した後であればまた話は違うかもしれません。
とはいえ先行者メリットという別の要素もあるので、このあたりはなかなか難しいところではあります。
過去の事例でいえば15年くらい前のSEOとか、5年ほど前のAIなどは、明らかに市場が過熱しすぎでありその中で十分な収益を上げ継続的にクライアントの満足度を高く保つというのは相当難しかったのではと思います。
前述した外注の内製化は、市場が過熱しているときには良い選択とは限りません。
そもそも市場がそのあと落ち込むであろうジャンルに手を出すこと自体、良い選択ではないと言えるでしょう。
つまり、当然すぎる話として、その市場は継続的に拡大成長を続けるのかを見極めるというのが一番重要なポイントの一つです。

当たり前すぎる話ですが、そこを見誤って回収できない投資をしてしまうケースが実際に山ほどあるのはこれまた事実です。
当社でも10年ほど前に「ビッグデータ検索」というジャンルのプロダクトを提供したことがありますが、これは見事に市場を読み誤りました。
ただむしろこれから立ち上がる面白い市場の一つでもあると考えています。
重要視すべき顧客体験
ところでそうした市場の継続性を判断する際の要素として、今回のコラムの冒頭でも書いた「それはどっちを向いているのか」というのがかなり重要なポイントなのではないかと思います。
もっというと、マーケティングソリューションというのは最終的には消費者にとってメリットがあるはずであるのに、消費者のほうを向いていないツールというのは市場が過当競争かそうでないか以前の問題です。
例えば今ではもう通用しなくなった、「被リンクを貼りまくればSEO効果が上がる」というアプローチなどはその典型ではないでしょうか。
SEOというのは結局良くも悪くもGoogleがどう判断するかにかかっているわけですが、当初のページランクの考え方(良いページからリンクが貼られていればそれは良いページのはず)の隙をついた(たいして良いページからでなくても大量のリンクを貼れば良いページ扱いされる)全く消費者目線でないアプローチが衰退するのはこれは当然のことだと言えます。
最近でも「とにかくユーザが誤クリックしやすいようなバナーを作る」とか、マーケティングの範疇ではないかもしれませんが「退会導線とステップを限りなく面倒くさくする」なども同様ではないかと思います。
対照的に良く言われるのがNetflixの退会や休会のしやすさです。
むしろ最近では長期ログインしていないユーザにNetflixが休会を勧めて反応がなければ一方的に休会、ということすらやっているようです。
ECのマーケティングソリューションでも、消費者よりセラー(ブランドとリテール)の方を向いているツールというのをたまに見かけます。
一時的に消費者をその気にさせる、とか、長期滞留在庫を販売しやすくする、などは、その結果消費者が満足してくれるのであれば悪いことではないですが、そこを無視したアプローチは継続的には通用しないのは当然です。
消費者のCXの向上を最優先する、といういわば当たり前のステップを常に最上位に置いておくことが出来れば、その市場は取り組むべき市場なのかどうかの判断も出来ますし、また取り組む意義がある市場だったとしてもその市場は自社が競争していくことが出来る市場なのかどうか、ということも必然的にわかるのではないかと思います。
ただそんな綺麗事だけで話が済めば簡単で、それに加えて「エンジニアはどうあるべきか」「販売戦略はどうあるべきか」「教育体制はどうあるべきか」「参入障壁はどう築くべきか」「自社のマーケティングはどうするべきか」など、いわゆる事業戦略も合わせて必要ですが、それらはまた機会を改めて触れてみたいと思います。
■関連コラム■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【著者情報】
ZETA株式会社
代表取締役社長 山崎 徳之
【連載紹介】
[gihyo.jp]エンジニアと経営のクロスオーバー
[Biz/Zine]テクノロジービジネスの幻想とリアル
[ECZine]人工知能×ECことはじめ
[ECのミカタ]ECの役割
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【公式SNS】
Xアカウント
Facebookアカウント
【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】







