レビュー によるECの役割の拡大
レビューエンジン導入キャンペーン
先日、当社のレビューエンジンについて契約期間を通常最低一年のところ、半年から契約可能なキャンペーンを発表しました。
一年だと少しハードルが高いけど、半年から利用可能なら使ってみたいという企業様がありましたら、是非ご連絡ください。
さて レビュー の価値、役割などについては過去にも何度かこのコラムでも触れていますし、また最近のセミナーなどの登壇では毎回紹介していますが、今回はECにおける レビュー の重要性ではなく レビュー によるECの役割の拡大、という視点についてです。
そもそも今となってはECというかイーコマースをコマースと切り離して考える事自体がナンセンスではあるのですが、実際のところはまだこの2つには事業としても予算としても組織としても大きな壁がある企業が多いのが実情です。
いつかはこの壁はなくなるのでしょうが、その後押しをする要素の一つが レビュー ではないかと考えています。
そもそも当社がサイト内検索・商品検索につづいてこれだけ レビュー に力を入れているのは、 レビュー による購買のアップリフトの余地がとても大きいと思うからです。
CRO には「 カゴ前 」と「カゴ後」がある
ちょっと話が飛びますが、デジタルマーケティングを考えるとき、サイトへの流入すなわち広告やSEOと、流入後すなわち CRO と2つに大別することができます。
当社は主に CRO に注力しているわけですが、 CRO も「 カゴ前 」と「カゴ後」の2つに分けることができます。
世の中を見てみると、カゴ落ち対策のソリューションはたくさんあり、またそれらの広告や宣伝もよく見かけます。
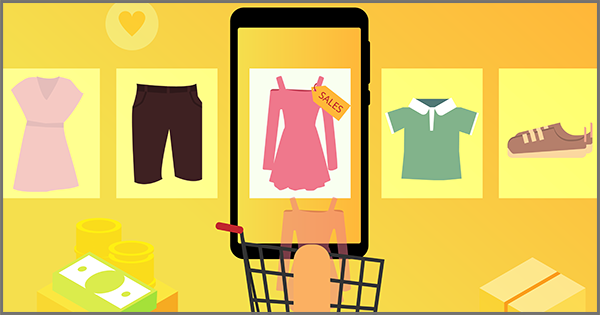
一方で当社が手がけるソリューションは、 カゴ前 に寄与する割合が高いといえます。
商品検索エンジンなどはほぼ100%、カゴ前すなわちいかに商品を見つけてカゴに入れてもらうかというための製品ですし、レコメンドもまたしかりです。
レビュー は、両方にまたがっているともいえます。
レビュー に後押しされてカゴに入れる、カゴに入れた後 レビュー を見て購買へと進む、これはどちらもありえるでしょう。
なぜ当社が カゴ前 に注力しているかというと、これも前述した内容と同様、 カゴ前 のほうが購買のアップリフトの余地が高いと思っているからです。
「 カゴ前 」と「カゴ後」の重要度
もちろん、一旦カゴに入れてもらった商品が購買にいたらない、すなわちカゴ落ちを防ぐというのが有効なのは間違いありません。
ただ、カゴ後のソリューションがたくさんあるのは、その重要さだけではなく、「カゴ落ち対策」というのがマーチャントに対して訴求しやすいソリューションであること、また効果を上げる施策を出しやすいことも、その理由の大きな部分を占めているような気がします。
そしてそうしたある意味、やったほうが良くて差別化しにくいジャンルは、我々ツールベンダーからするとレッドオーシャンになりやすいのです。
一方で カゴ前 というのは、これはなかなかソリューションとしては大変です。
サイトに訪問したユーザーにいかに商品を効率よく発見してもらって、カゴに入れる気持ちにさせるかというのは、一筋縄ではいきません。
でも逆に、良いソリューションが提供できればそれはツールとしては差別化しやすく、レッドオーシャンになりにくいという側面もあります。
普通に考えて、サイト流入からカゴに入れるまでのアップリフトの余地のほうが、カゴ落ちを防ぐことによるアップリフトの余地より高いことは、ごくごく自然だと言えるでしょう。
商品検索と レビュー 連動による効果
サイト内検索エンジンについてはその処理速度や機能において、圧倒的な存在感を示すことが出来るようになりました。
導入先の流通総額はもう一兆円を越えようとしていますし、いまだに当社の商品検索から他社の検索エンジンの切り替え事例は0件です。
そこに加えて レビュー という強力な武器を用意し、また商品検索と連動することができれば、これは CRO のうちでもカゴ前のアップリフトにそうとう効果があるのは容易に想像できます。
レビュー の存在自体が商品の価値を見定めやすくすることでアップリフトするという側面もありますが、 レビュー のデータ自体で検索結果の精度をより高めて、少ないアクションでよりユーザーにピッタリの商品へと誘導することができるようになるためです。
一旦 レビュー が当たり前になると、そのうち起こるのは「 レビュー が少ない商品には手を出しづらい」という現象です。
私が思うにあと数年もすれば、 レビュー 無しもしくは レビュー が少ない商品を買うのはアーリーアダプターであり、それらを参考に商品を買うのがレイトマジョリティとなっていくでしょう。

レビュー のメディア化
そしてここで重要なのが、「 レビュー という機能はデジタル以前には存在感が低かった」ということです。
もちろんEC以前でも、雑誌や情報サイト、ブログなどで レビュー を見ることはありましたが、EC自体に レビュー 機能がある場合、その母数や信頼性は大きく変わってくるでしょう。
そうなると、「デジタルではない購買でも、今までよりもそうした情報を参考にしやすくなる」のは必然です。
つまりECに レビュー 機能がつくことで、店頭での購買も後押しされるということです。
そうなるとECは、これまでの「デジタル上での購買」という役割から、「デジタル上での購買と、店舗での購買の後押し」というように役割が拡大していくということです。
これこそまさに、以前に述べた、オウンドメディアのアーンドメディア化です。
またもう一つというかさらに重要なのが、「店舗で購入した場合でも レビュー の投稿先がある」という点です。
もちろんこれまでも価格.comとか、独立した レビュー の投稿先というのはありましたが、それよりも自分が購入したマーチャントのEC媒体のほうがはるかに投稿の敷居は低くなりますし、またマーチャントも投稿のインセンティブを提供しやすくなります。
オムニチャネル化において次に目指すもの
つまりマーチャントは、店舗購買についてもその商品のECメディア上に口コミの投稿を促すことで、さらに店舗やECでの購買のアップリフトを狙うというスパイラルが作れるようになるということです。
これは、かなり大きな変化ではないでしょうか。
こうなるとデジタルという括りはあまり重要ではなく、真の意味でECもコマースのマーケティングの一部となりうるわけです。
それはひとえに、デジタルという情報の双方向性によって起きる変化というか革新だと言えるでしょう。
ECすなわちデジタル上の購買「のみ」では、通信では双方向でも情報流通という観点では双方向ではなく、 レビュー によって情報としても双方向になるのです。
もちろんその実現のためには、店舗で購入した商品をEC上でも容易にたどり着けるようにするという機能が必要です。
これはまさにオムニチャネルの次のステージだと言えるでしょう。
当社でもこの店舗・ECの商品や レビュー 連携は開発を進めており、近々発表する予定です。
■関連コラム■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【著者情報】
ZETA株式会社
代表取締役社長 山崎 徳之
【連載紹介】
[gihyo.jp]エンジニアと経営のクロスオーバー
[Biz/Zine]テクノロジービジネスの幻想とリアル
[ECZine]人工知能×ECことはじめ
[ECのミカタ]ECの役割
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【公式SNS】
Xアカウント
Facebookアカウント
【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】









