ECのトレンド
ゼロスタートは主にEC事業者様向けに、「ZERO-ZONE」 という製品ソリューションの提供をしております。ここまで4製品をリリースしており、以下の様なラインナップになっています。
商品検索エンジン ZERO ZONE SEARCH
レコメンドエンジン ZERO ZONE RECOMMEND
効果測定エンジン ZERO ZONE FEEDBACK
ビッグデータ向け検索エンジン ZERO ZONE DISCOVER
この中でも主力製品は商品検索エンジンとレコメンドエンジン ZERO ZONE RECOMMENDです 。
これらのソリューションを提供してきたことによる弊社の考えると ころのECの現状や未来、そしてECにおける検索やレコメンドのありかたなどについて解説していきたいと思います。
ECを取り巻く状況
第一回目はECを取り巻く状況についてです。
以前はECは、一部の新しもの好きな人たちのものでした。マーケティング用語で言うところのイノベーターやアーリーアダプターといわれるクラスタです。
個人情報の登録やクレジットカードによるオンライン決済に対する不安からECの利用に二の足を踏む人は多かったかと思います。

ところがPCはもちろんのこと、スマートフォンの普及によっていつでもどこでもECサイトにアクセスできる環境が整ってきたこともあり、アーリーマジョリティやレイトマジョリティがEC利用者層として参入し始めています。
こうなってくると利用者(流通額)の向上→ ECショップの各種指標の向上(店舗数、取扱商品数、 商品到着までの時間、手数料の低減など) というスパイラルに突入し、これからもまだまだEC利用比率は伸びていくことでしょう。
日本のEC化率は2012年の段階で3%とまだまだ低い(欧米は5-7%程度)ですが、逆に言うと伸びしろが多いということでもあります。
進むECの大衆化
EC化率が上がるということは、 裾野が広がるということでもあります。これによりECは「物好きな人向け」から「一般の人向け」 になっていくと思われます。扱われる品目も変わっていくでしょうし、決済手段も変わっていくでしょう。
これはECがインフラとなっていくのに必要なステップであるといえます。
そしてEC上で要求されるマーケティングロジックというか、商売の勘所も変わって行きます。
初期のECは主に本やCD・DVD、そして小物家電が占める割合が高かったといえます。以前のAmazonはまさにこういった商品をメインで扱っていました。
ただ個人消費の内訳でいえば、なんといってもその比率が高いのは食品です。エンゲル係数という指標があるように、飲食費というのは消費のなかでも重要なものです。
レコメンド昔は? 今は?
Amazonといえば当初協調フィルタリングによるレコメンドが 一躍脚光を浴びました。
この協調フィルタリングというアプローチは、書籍やCD・DVDにおいてはかなり高い精度というか良いレコメンド結果を出すことが出来ます。
一方食品や生活雑貨では、 それほどの効果を上げることは出来ません。
「Aを買っている人はBも買っています」 という考え方が良く当てはまるケースもあれば、 そうでないケースもあるということです。
今後のECの伸びしろは、 協調フィルタリングはうまく当てはまらないケースのほうが増えて いく可能性が高いと思います。
また、スマートフォンの普及は裾野の拡大以外にもECに影響を与えています。
最近はオムニチャネルという言葉が取り沙汰されていますが、 これは要は実店舗とECをまとめて扱おうというものです。(オムニというのは全てという意味です)
以前はO2Oという言葉が話題でしたが、 これをより拡大した考えたです。
このテーマは広大なので詳しくはまた別の回で解説しますが、オムニチャネルやID-POSデータの活用にはスマートフォンの普及が今後大きく寄与すると思われます。
たとえば最近の事例ですとpaypalの顔パスというサービスが、今後のオムニチャネルの一つの可能性を示唆しているような気がします。
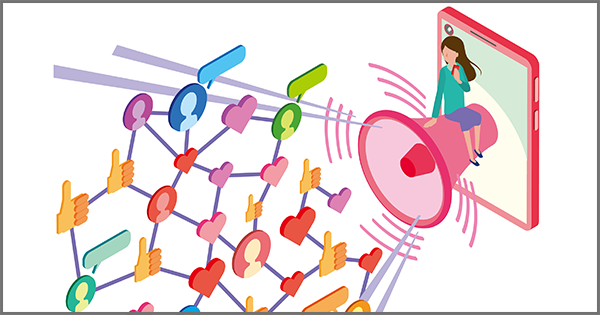
PCにないスマートフォンのメリットとしては、位置情報が取れる、決済端末になりうる、などがありますがやはり最大のメリットは「たいがいそばにある」ことでしょう。
EC利用端末の比率としては、今後どんどんスマートフォン>PCという図式が拡大するのは、 これはまず間違いないことだと言えます。
ECトレンド のまとめ
・「取引回数、金額、扱い品目数など各種の指標が伸びている」
・「ユーザーの裾野が拡大している」
・「実店舗との連携が始まろうとしている」
などが挙げられます。
これらの ECのトレンド に一貫して言えるのが「ECは店員という機能を必要とし始めている」ということです。
次回はその点について考察してみたいと思います。
■関連コラム■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【著者情報】
ZETA株式会社
代表取締役社長 山崎 徳之
【連載紹介】
[gihyo.jp]エンジニアと経営のクロスオーバー
[Biz/Zine]テクノロジービジネスの幻想とリアル
[ECZine]人工知能×ECことはじめ
[ECのミカタ]ECの役割
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【公式SNS】
Xアカウント
Facebookアカウント
【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】









