カスタマーエクスペリエンス と透明性
最近参加した海外イベントのご紹介
先日とある海外のイベントに勉強のため参加してきました。
その中で一つ、かなり参考になるセッションがあり、自分としても考えがかなり整理できたので、ちょっと紹介したいと思います。
そもそもイベント全体のテーマは カスタマーエクスペリエンス (CX)でした。
カスタマーエクスペリエンス という単語自体、日本ではトレンドワードにはなっていません。
そもそも カスタマーエクスペリエンス ではなく顧客エクスペリエンスとか顧客体験と訳されているケースもありますが、顧客と訳してしまうと真意が伝わらないとは思いました。
日本でなぜCXが流行っていないのかは正直わかりません。
UXはUI・UXという組み合わせで一時期かなりバズワード化しましたが、CXのほうがより重要な概念だとは思います。
そもそもマーケティングに関するトレンドワードは、ビッグデータ・O2O・オムニチャネル・マーケティングオートメーション・DMP・AIなど次から次へと現れては消えていきます。
(AIはマーケティングだけではないですが)
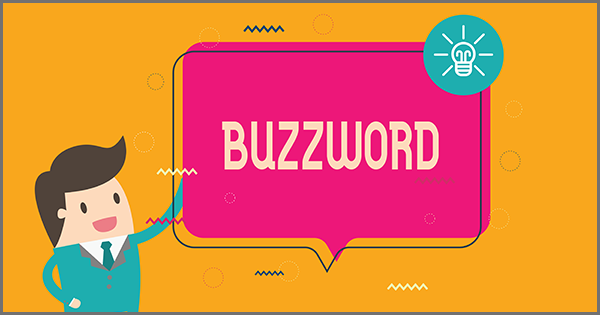
以前から私は、こうした続々と登場するトレンドワードもしくはバズワードは、結局マーケティングに関する各側面を切り取っているだけで、本質は同じです、ということを訴えてきました。
そしてそれは「パーソナライズ」という考え方に集約されると表現していたのですが、このCXという考え方のほうがよりしっくり来る、とこのイベントを通して感じました。
カスタマーという言葉のニュアンス
パーソナライズは概念でもありますが、手段・道具でもあるので、一連のトレンドワードに通じるといいつつ、それ自身も道具ではあるな、という感じはしていたのですが、CXであれば完全に概念と捉えることができるためより高次というか全体を通していえるキーワードだ、というのが率直な感想です。
ただこれは、日本で言われている カスタマーエクスペリエンス とはちょっと違うとも感じました。
推測するに、カスタマーと顧客はちょっと違う意味なのが理由の一つではないかと思います。
カスタマーというかcustomerを表現できる日本語があまりないのです。
強いて言えばむしろ消費者だと思います。
直訳すれば消費者はcustomerではなくてconsumerですが、こういう核心に近いキーワードは直訳だけではなくてその国の文化や背景も交えないと適切な変換ができません。
USでconsumerというと、完全にconsumeする人を指しています。
つまり何らかの商品を購入して、それを消費(consume)している状態の人のことです。
逆にcustomerというと、なんとなく漠然とお客さんという感じです。
日本では逆に、customerの直訳である顧客のほうが、商品を購入した状態のお客様、という感じで消費者というと商品を購入して消費している状態というよりは、いわゆる一般消費者というイメージだと思います。
つまり、customerとconsumerが直訳とは(完全にではないですが)反対の使われ方をしているような一面があり、 カスタマーエクスペリエンス を顧客体験というとむしろconsumer experienceのような印象になってしまうのではないかということです。
もちろんカスタマージャーニーという、まあまあトレンドワードになっているキーワードもありますが、カスタマージャーニーはむしろjourneyのほうに目が行くので、それがuser journeyでもcustomer journeyでもconsumer journeyでもあまり意味に違いが出ない、あとカスタマージャーニーという響きはなんとなく聞こえがいい、という理由もあってまあまあトレンドワードになっているのではないでしょうか。
〜 カスタマーエクスペリエンス 〜 CXとは
さて、CXを一番根幹の考え方として捉えると、各種マーケティングトレンドワードを実にすっきり整理することが出来るようになります。
その前にそもそもCXとは何か、を私なりに説明してみたいと思います。
CXとは、商品を認識してから購入に至るもしくは至らない、購入した場合はそれを消費(使用)するという一連の流れの全てにおける体験、つまりあらゆる消費者体験のようなものです。

繰り返しですが顧客体験だとなんとなく購買後のイメージになってしまうのではないでしょうか。
CXがそうした全体を表すものである場合、ビッグデータはそこで利用される材料、O2Oは店舗やオンラインを行き来する導線、オムニチャネルはCXにおける商品物流、AIはそれらを処理する道具、パーソナライズはより個々人に特化したマーケティングをするというアプローチ、カスタマージャーニーはCXにおける道筋、DMPは処理するデータの保管場所、といった感じです。
余談ですがCXという概念があると、オムニチャネルの位置付けがよりはっきりします。
オムニチャネルは顧客のあらゆるタッチポイントをカバーするアプローチ、とされていますがCXを前提とすればCXがそもそもそうしたものなので、その中でも商品物流をメインに据えているのがオムニチャネルとも考えられます。
ただCXはこうした概念そのものであるため、ソリューションプロバイダーはCXを売りにすると何を商品化していいかわからない、という側面もあるため、それを個々に切り出して「ビッグデータソリューションです」「AIソリューションです」「オムニチャネルソリューションです」と言っているのかもしれません。
私も以前はCXという言葉をそこまで完璧に、かつ重要なものとして把握していたわけではなかったので、しいて言えば一番核心に近い「パーソナライズ」をメインに据えた表現をしてきましたが、今後はCXを中心に据え、パーソナライズはそのためのアプローチ、という以前よりももう一歩俯瞰した考え方を広めていければと思います。
さてでは、ゼロスタートではCXの何をビジネスにするのか、今メインとなっているサイト内検索・商品検索エンジンやレコメンドエンジン、広告最適化エンジンはどういう位置付けになるのかですが、そのためには「透明性」という考え方が大変重要であると、やはり先日のイベントで感じました。
次回はこの「CXと透明性」について述べてみたいと思います。
■関連コラム■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【著者情報】
ZETA株式会社
代表取締役社長 山崎 徳之
【連載紹介】
[gihyo.jp]エンジニアと経営のクロスオーバー
[Biz/Zine]テクノロジービジネスの幻想とリアル
[ECZine]人工知能×ECことはじめ
[ECのミカタ]ECの役割
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【公式SNS】
Xアカウント
Facebookアカウント
【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】









