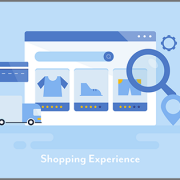EC商品検索・レコメンドで接客を実現するには
0件ヒット を回避するEC商品検索に期待されること
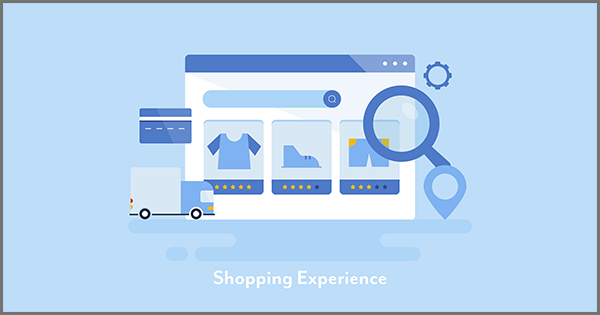
今回は前回に引き続いてECサイトの接客と検索・レコメンドについて考えてみたいと思います。
前回の記事で、検索はECサイトにおける接客というか店員であると書きました。ただこれまでにECサイトで実装されているサイト内検索は、単純な検索機能を提供しているだけのものが多いのも事実です。
0件ヒット というのが一番わかりやすい例ですね。

例えば書店にある書誌検索の端末を思い浮かべてみると良いと思います。
店員さんがいなかったり接客でふさがっている場合、書誌検索の端末があればそこで探すことが出来ますが、例えば書誌名を間違えていると 0件ヒット になってしまいます。
ところが店員さんに聞けば、書誌名を間違えて伝えてもだいたい察して正しいありかを教えてくれます。
旧来のEC商品検索は書誌検索端末のようなものですが、これからのEC商品検索は店員のような挙動が期待されているということです。
レコメンドが上手くいくケースと上手くいかないケース
レコメンドは、元々商品のオススメ機能なので本質的にそういう役割なはずですが、現在実装されているレコメンドのほとんどは協調フィルタリングの代名詞です。Aを買った人はBも買っていますというものです。
もちろんこの手法は有効ではあるのですが、商品ジャンルによってかなりその効果が左右されます。
例えば小説やマンガ、映画などは「Aが好きな人はBも好き」というのが結構あてはまります。
初期のAmazonは主にそういった商品を扱っていましたし、レコメンドで有名なNetflixなども同様です。
ところが生活雑貨とかアパレルなどでは、うまくいくケースもありますがうまくいかないケースも多々あります。
「ビールを買う人はオムツを買う」というのは有名な事例ですが、むしろこういったケースは稀でしょう。
まとめると以下の様な感じになります。
旧) 検索 → 入力条件に従うだけの検索
レコメンド → 協調フィルタリング
新) 検索・レコメンド → 店員による接客のような商品提案
EC商品検索・ レコメンド で接客を実現するための4+1の要素
では接客のような検索・ レコメンド を実現するにはどうすれば良いのでしょうか。
これには大きく4+1つの要素があります。
1. 商品を知る
2. お客さんを知る
3. お客さんと商品のマッチングを考える
4. 商品を提案するタイミングを考える
5. 継続的な改善
5は実現するために必要というより、1-4のレベルアップですので4+1としています。
[要素1] 商品を知る
まず1ですがこれは当たり前のことですね。
商売をやる以上商品知識は最も重要なものの一つです。
ただECで良くあるのが、商品の情報がきちんとEC上に反映されていないということです。
「商品の情報」には何があるでしょうか。
商品名、メーカー、価格などはもちろん、ジャンル、サイズ、色、評価などそれらは多岐にわたります。それだけでなく「今話題の商品」とか「こういった人に好まれる」という情報も商品情報です。
ところがだいたいECサイトで登録されるのは、正式に公開されているスペックだけではないでしょうか。
店舗の接客を考えてみれば、正式な商品情報だけだと「◯◯はありますか?」という相談には回答できますが、「△△に使うものは何が良いでしょうか」という相談には回答できません。
先ほどの書誌情報端末と店員がまさにそういう対比です。新人店員とベテラン店員という比較でも良いかもしれません。
ECサイトを運営するのであれば、メーカーから提供される正式な商品スペックだけではなく、それに加えてその商品をお客さんに提案するための知識と経験が必要です。
店舗の店員であればそれが頭のなかにあるだけでも接客はできますが、ECサイトにおいてはテキストなどの情報にして登録をしなければお客さんへの商品提案には使えません。
この「商品知識を明文化する」という作業は、EC特有の作業であるといえます。
[要素2] お客さんを知る
実はこれができているECサイトというのはほとんどありません。
しいて言えば商品の閲覧履歴や、協調フィルタリングでユーザーの購買履歴を活用しているくらいです。
もちろん商品ジャンルによっては、お客を知らなくても良い物もあります。いわゆる万人にオススメできるようなものですが、そういったものはあまり多くはないでしょう。
こちらも実際の店舗に比較して考えてみると、例えば常連さん相手の接客であれば相手の人となりがわかっているので良い商品の提案が可能です。
仮に一見さんだとしても、性別、年齢、来店時の服装、誰と来ているかなどは重要な情報ですし、良い商品提案をしようとすればお客さんの需要を良くヒアリングすることが重要でしょう。
ECサイトにおける検索での入力の重要性
ECサイトの場合、お客さんを知るために出来ることが実際の店舗にくらべて多くはありません。
デモグラフィックが取れていればそれは重要なヒントになります。
あとは閲覧履歴や購買履歴などもですが、これらは現在でもそれなりに活用されてたとえばリターゲティング広告などに使われています。
それらに加えて重要なのが、ECサイトの検索での入力です。
まさにこれはお客さんから能動的に「こういったものを探しているんですが」という相談をされている状態です。
店舗接客の場合、お客さんから相談される場合はもちろん、場合によっては店員からアプローチして需要をヒアリングすることが出来ます。
ところがECサイトの場合には、サイト側から接客のアプローチをすることができません。
店舗であれば「迷っているようだ」とか「見つからなくて困っているみたいだ」という状況がわかりますがECではそういったことはわかりません。
たとえばページ遷移やヒートマップを瞬時に活用して、困っていそうなユーザーに「探しものは何ですか」とポップアップを出すことも出来るかもしれませんが、そういったことの実現にはまだ時間がかかることでしょう。
となるとお客さんが検索をしてくれているタイミングこそ、最も貴重な接客のタイミングと言うことが出来るのです。
お店側からアプローチ出来ない以上、お客さんからのアプローチは実際の店舗以上に重要なチャンスです。
この2こそが、今まさにECサイトに求められていることなのです。
1と2が揃えば、あとは3と4、すなわちお客さんと商品のマッチングをする、その内容を提案するタイミングを図るという手順に進みます。
次回はこの3と4について解説してみる予定です。
■関連コラム■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【著者情報】
ZETA株式会社
代表取締役社長 山崎 徳之
【連載紹介】
[gihyo.jp]エンジニアと経営のクロスオーバー
[Biz/Zine]テクノロジービジネスの幻想とリアル
[ECZine]人工知能×ECことはじめ
[ECのミカタ]ECの役割
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【公式SNS】
Xアカウント
Facebookアカウント
【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】